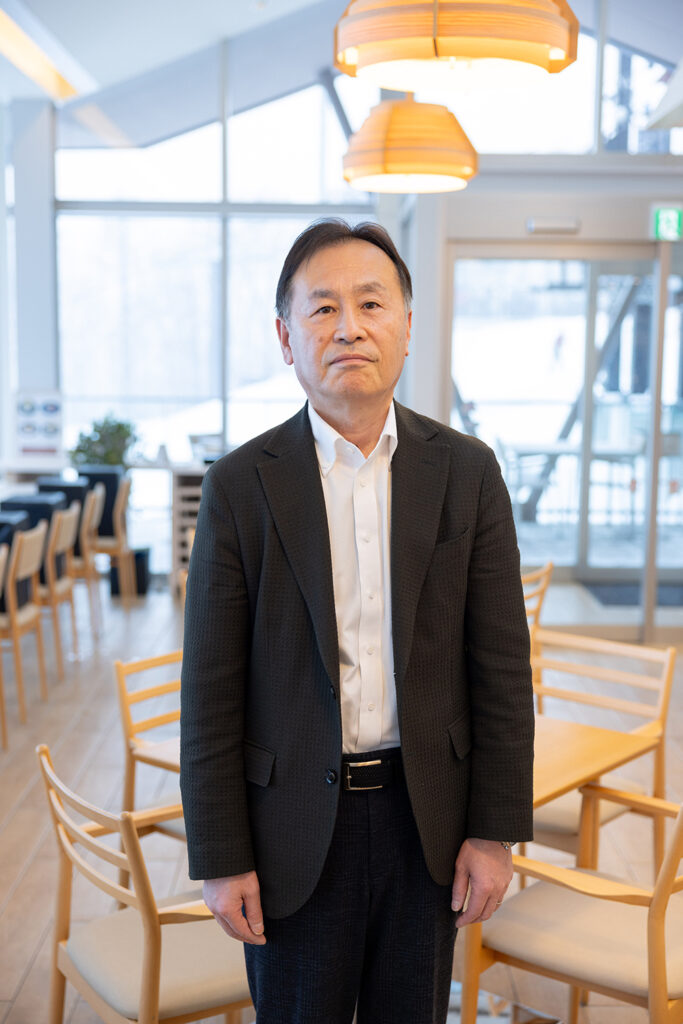川村 洋介さん
温泉と下流域をつなぐ草津のもうひとつの要、中和事業とは?
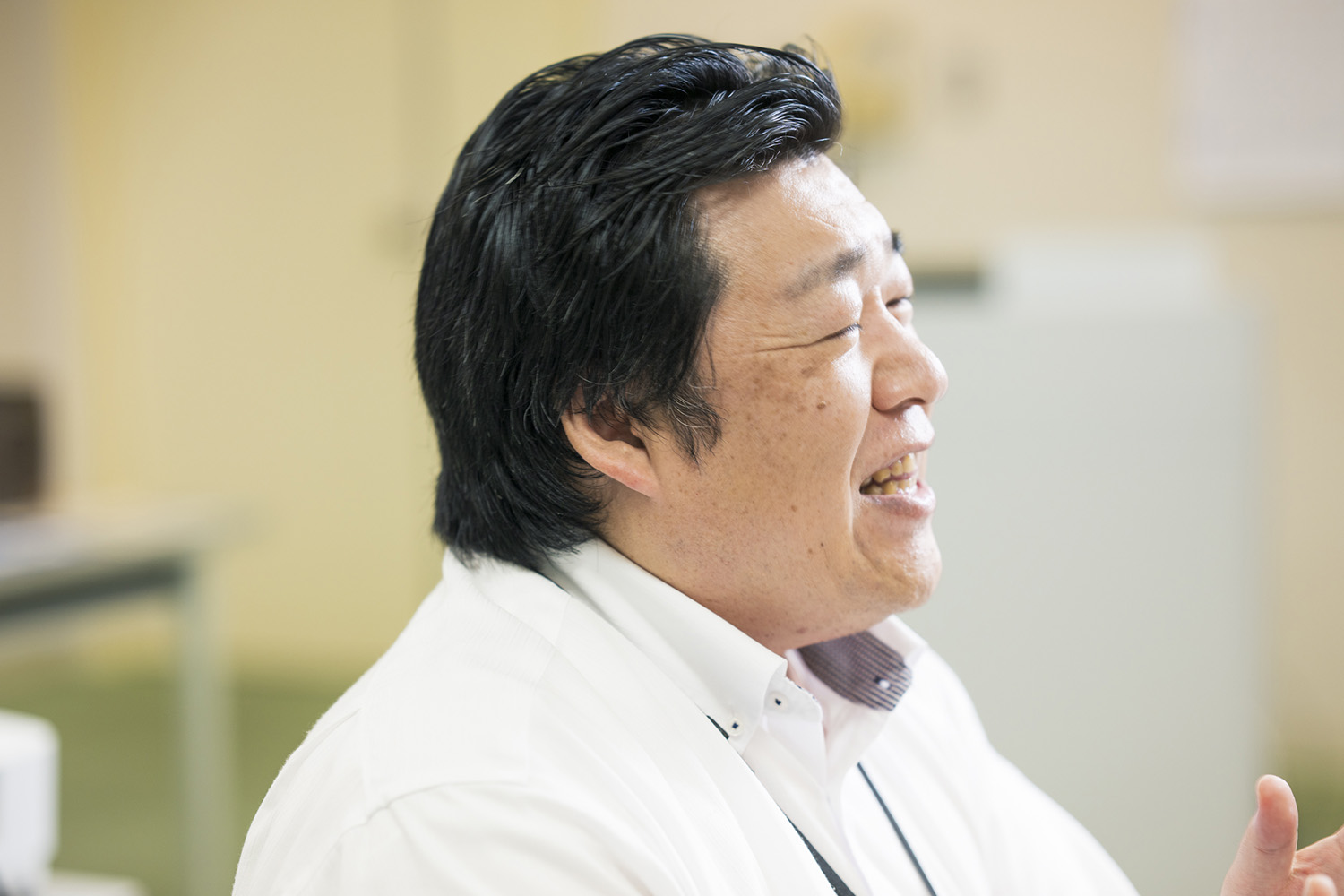
まず初めに、草津温泉と切っても切れない「中和事業」について改めて教えてください。
川村:はい。草津の温泉街を流れる「湯川」は、草津白根山から湧出する強酸性の温泉水が集まって流れる川です。pH2.0前後という強い酸性で、そのまま下流に流れれば農業や生活用水には使えず、建造物の設備を腐食させるといった深刻な影響を与えてしまいます。実際、かつて吾妻川は魚が棲めず「死の川」と呼ばれ、下流の農家の方々は畑に石灰をまいて何とか耕作を続けていた歴史がありました。そうした状況を改善するため、群馬県が調査を行い、最終的に国が引き継ぎ、世界初の取り組みとして1964(昭和39)年に「中和事業」がスタート。現在国が直轄で行っている中和事業は、草津と秋田の玉川温泉の2カ所だけです。
そもそも“中和”という言葉に馴染みがない方も多いと思うのですが、具体的にどういった仕組みなのでしょうか。
川村:簡単に言えば、「酸性の水に石灰を加えて中性に近づける」というものです。石灰を粉砕して水に溶かし「石灰ミルク」と呼ばれる液体にして、湯川・大沢川・谷沢川に投入します。これによって酸性水は中和され、草津町から約3km下流にある品木ダムに水が集まる時点では、pH5~6程度に調整されています。エメラルドグリーンの湖水が広がり「上州湯の湖」とも呼ばれる品木ダムは、中和生成物を沈殿させる役割を担う特別なダムで、その水は同時に水力発電にも利用されます。流れて出た水は利根川へとつながり、首都圏の水源の一部を支えるまでになります。
なるほど。ダムにたまった沈殿物はどのように処理しているのでしょう。
川村:湖底に沈殿し堆積する中和生成物は定期的に取り出して、産業廃棄物として適切に管理。法律に基づき山中の処分場に埋め立て処理をしています。60年近く積み重ねてきたことなので、膨大な量になりますが、これもまた私たちの大切な仕事の一部です。
こういった作業は24時間365日止められないが故の大変さもあると思います。
川村:そうですね。温泉はこんこんと自然に湧き続けていて、誰も止められるものではありませんから。だから中和事業は一日たりとも休むことができません。台風や大雨のときは深夜でも職員が出て放流操作を行います。ダムの水位が限界を超えると構造上大きな影響があるので、土日や夜間も関係ありません。

そして、この場所はどなたでも見学できるのですよね。
川村:2004年からこの中和事業は「環境体験アミューズメント」として一般の方にも随時見学していただけるようになりました。学校の社会科見学や団体のほか、個人の方でも事前に申し込めば職員が直接ご案内します。見学では、酸性水に石灰石粉を混ぜる現場やペハノン紙を使って湯川のpH値が測れる実験、さらには中和事業の歴史までを体験的に学べます。訪れた方は「草津でこんな事業をやっていたなんて知らなかった」と驚かれ、帰るころには「見学してよかった」と言ってくださる方がほとんどです。自然の恩恵である温泉を「浸かる」だけでなく、「守る」側面まで体感できるまさに環境教育の場だと思っています。
草津にとっての「中和事業」はどのような存在だと考えていますか。
川村:中和事業は草津町に拠点はあるものの、下流の水質を守ることで下流に住む人々の生活を守る重要な国の事業です。仮にこの事業を続けなければ、かつての「草津が温泉で栄える一方で、下流の生活は苦しむ」という構図になりかねません。だからこそ、中和工場が稼働することで草津と下流域が共存できるといえるのではないでしょうか。実際、下流の地域に住む方から「昔は畑に石灰をまいて大変だったけれど、中和工場ができて生活が変わった」と直接感謝の言葉をいただきました。そういう声を伺うと、自分たちがやっていることは草津だけのためではなく、流域全体の暮らしを支えているのだと実感しますね。
草津の温泉は町の誇りであり観光資源ですが、その裏側で発生する強酸性の湯を放置すれば豊かな自然や農業、日々の生活が脅かされてしまう。だから中和事業は“草津温泉の守護神”ともいえるのではないでしょうか。観光で訪れる人たちにとっては見えにくい部分かもしれませんが、陰で支えるこの仕組みがあるからこそ、草津の温泉が安心して楽しめると思います。
3回の赴任で映し出す、草津の変化と自らの思い

川村さんがこの仕事を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
川村:生まれてから20年間ずっと出身地である東京・大田区で暮らしました。高校を卒業した後は「東京法律専門学校(現在の東京法律公務員専門学校)」に進学し、公務員になるための勉強をしました。そこには公務員試験に特化したコースがあり、クラスメイトもみんな公務員志望。切磋琢磨しながら過ごした時期です。
実は、警視庁と国土交通省の両方から内定をもらっていました。子どもの頃は警察官に憧れていて、幼稚園の卒園アルバムにも「先生を守る警察官になる」と書いていたほどで(笑)。ただ、警察学校での半年間の厳しい訓練の話を聞いて気後れしてしまったのと、ずっと大きな国道沿いで暮らしてきて道路行政に関心があったこともあり、国交省を選びました。それと、20年間実家暮らしだったので、一人暮らしをしたい気持ちも後押ししましたね。
そして最初の勤務先がここ草津町だったのですね。
川村:はい。ただ、草津という名前は知っていましたが、群馬県のどこにあるのかも正直分からなかったんです。赴任先を告げられて初めて地図を開き、「群馬の端っこにあるのか」と知ったくらいです。事前に赴任地を見に来ますかと上司に言われましたが、自宅から遠かったこともあり「大丈夫です」ときっぱりお断りしたのも今となってはよい思い出です(笑)。就職が決まり、とにかく新生活を楽しみにしていたのを記憶しています。
初めての草津勤務、どんな日々でしたか。
川村:当時は独身だったので休日に湯畑周辺を散策する程度でしたね。今のようにカフェや若者向けの店が多くはなく、観光客も団体旅行で訪れる高齢の方が中心。町全体に落ち着いた雰囲気が漂っていて、若者が気軽に楽しめる場所は少なかったように思います。正直なところ、最初の4年間の赴任では地元の方と深く関わる機会もほとんどなく、「観光地としての草津」を遠くから眺めているような感覚でした。

最初の草津勤務から、すでに3回赴任されていますね。
川村:私たち国家公務員は、基本的に数年ごとに必ず異動があります。なので、同じ場所に長く勤めることはレアなケースといえるでしょう。私も草津を離れて別の地域に勤務しては、また数年後に戻ってくるという形で、これまで草津に3回赴任してきました。事務所の資料を見ると、現役職員の中では草津の勤務期間が最も長いという記録を更新し続けているようです。
2度目の赴任では、どんな変化を感じましたか。
川村:2015年に戻ってきたときには、結婚して子どももいて、最初に一人で草津に来たときとはまったく状況が異なっていました。子ども園に通わせたり、保護者同士で交流したりするなかで、自然と地域に溶け込んでいけましたね。飲食店やイベントにも足を運ぶようになり、「草津ってこんなに明るい町だったんだ」と驚く日々の連続でした。若い観光客や女性も多く訪れるようになり、町全体が開放的に変化しているのを実感。自分のライフステージの変化と、時代とともに進化する草津の姿が重なったのが2度目の赴任でした。
そして現在、3度目の赴任を迎えています。どんな思いで草津にいますか?
川村:3年ぶりに草津に戻ってきた時、親交のあった方々から「久しぶり」ではなく「おかえり!」と声をかけてもらえたのが本当に印象的でしたね。子どもも小学校で子ども園時代の同級生から「覚えてるよ!」と迎えてもらい、町全体で家族ごと受け入れてもらっていると実感しました。
そして、草津に住んでいると不思議と活力が湧いてきますね。温泉がこんこんと湧き出る力や、地下のマグマのエネルギーが自然と人々に伝わってくるのかもしれません。草津に来る前は正直、心身が少し疲れている時期があったのですが、草津での暮らしの中で少しずつ元気を取り戻していけた。これは自分にとって大きな支えになっていますね。
“知ってもらうこと”が未来を守る第一歩。見学を通じて中和事業を次世代へ繋ぐ

現在、川村さんはどのような業務を担当されているのでしょうか。
川村:現在は総務係長として、職員の勤務時間管理や給与のチェック、庁舎の維持管理など、いわば“縁の下の力持ち”的な事務を担当しています。それに加え、この品木ダム水質管理所では見学の案内も職員が直接行います。通常は外部に委託するのが一般的ですが、ここでは職員が自ら説明しますので私自身も案内役を務めていて、これは他の現場にはない特色です。
そこにやりがいを感じることも多いのでは?
川村:まさにそうですね。SNSやホームページで発信しているので、ここを目的に来てくださる方も増えてきましたし、旅行会社の紹介や学校の社会科見学で訪れる方もいます。多くの方が「全然知らなかった」と驚かれて、説明を聞いたあとには「本当に勉強になった」「来てよかった」と言ってくださるんです。最初は子どもの自由研究のために来たのに、最後はお父さんお母さんが真剣に質問されることも多いです。子どもは途中で飽きて走り回ってしまったりするのですが(笑)、大人も熱心に聞いてくださるのはうれしいですね。見学を通じて「中和事業ってこんなに大事な事業なんだ」と知ってもらえることが、自分にとって大きなやりがいになっています。

中和事業を町の人にどう伝えているのでしょうか。
川村:昔から「品木ダム水質管理所」という名称は町のパンフレットに載っていたので、皆さん存在は知っていたはずです。大滝乃湯の隣にある大きな施設ですから、草津で暮らしていれば目に入りますし、「あそこに工場がある」という認識はあったと思います。ただ、実際に何をやっている場所なのかはほとんど知られていなかったんじゃないでしょうか。
そこで、ある時当時の上司が吾妻郡や渋川市内の小中学校に手紙を出して、「理科や社会の勉強にもなるから、ぜひ見学に来てください」と呼びかけたんです。私も一緒に担当しましたが、とても良い取り組みだと感じていました。草津小学校や草津中学校から毎年見学に来てもらえるようになっていましたが、コロナ禍で一時中断してしまいました。そこで、コロナが明けた後に「草津の将来を担う子どもたちにこそ中和事業を知ってほしい」という強い思いで上司とともに両校へ直接お願いに伺いました。その結果、数年ぶりに見学を再開してもらうことができたのです。今後も継続していくことで、「中和事業を知っている」子どもや町の人を一人でも増やしていきたいですね。
最近は町の人や観光客に向けての広報にも力を入れているそうですね。
川村:はい。草津温泉に関わりのある有志の皆さんと一緒に、新しい地図作りにも取り組んでいます。これまでの地図は湯畑を中心に飲食店や観光スポットを紹介するものが多かったのですが、今回は「草津温泉のサイエンス」というコンセプトなんです。火山の恵みとして湧き出す温泉が入浴だけでなく、生活のインフラとしても利用されている、そして最後には中和事業が処理をして、下流域へとつながっていく。そうした“温泉の一連の流れ”を科学の視点から紹介する内容にしようという取り組みです。私自身も会議に参加して、中和事業の説明をさせていただきましたし、会議に参加している方たちに実際に現場を見学していただく機会も設けました。草津温泉の情報発信に地域の方々が主体的に関わり、中和事業もその一部として伝えられるのは、とても意義があることだと感じています。
守り続けること、変えていくこと。川村さんが目指す中和事業の未来とは

中和事業が始まって60年を超え、今後の課題や新しい取り組みについて教えてください。
川村:「酸性の川を中和し続ける」という役割自体は、これからも絶対に変わりませんし、変えてはいけないと思っています。ただ、方法については時代に合わせて進化していくはずです。いま私たちが行っているのは石灰を投入する方法ですが、研究者と協力しながら新しい可能性を模索しています。
たとえば、前橋工科大学の先生が進めている「電気分解による中和」の研究があります。酸性の河川水を装置に流し、電気分解によって中性に近づける。その過程で発生する水素を回収して発電に利用し、その電力で工場を動かすという仕組みです。現在は小規模な実験を定期的に行っている段階ですが、もし実用化できれば石灰の使用量を大幅に減らせます。運営コストの削減につながり、税金の負担を抑えることにもなります。環境負荷の軽減と持続可能性の両立を目指す試みとして、大きな期待を寄せています。
なるほど、期待が高まりますね。そのような中和事業を支える上で、川村さんが大切にしていることは何でしょうか。
川村:先輩方が24時間365日、一日も止めずに事業を続けてこられた積み重ねです。多少のトラブルで数時間止まることはあっても、丸一日止まったことは過去一度もないというのは想像を絶する努力の結果だと思います。毎日同じように見えて、実際には機械の不調や大雨への対応など、現場は常に変化があります。そうした緊張感の中で守り続けてきた先輩方の取り組みを、次の世代にもしっかり引き継いでいかなくてはいけないと思っています。

川村さんにとって、改めて草津という場所がどんな存在になっていますか。
川村:自分にとってはもう「勤務地」ではなく「帰ってくる場所」になっていますね。草津の温泉は体を温めるだけでなく、人の心も温めてくれると思います。中和事業は縁の下の力持ちのような仕事ですが、これがあるから草津の温泉文化が守られている。これからも草津と下流域をつなぐ役割を果たし、次の世代に「草津の温泉を守り続けたい」と思ってもらえるように努めていきたいですね。
「勤務地ではなく帰ってくる場所」と語る川村さんの言葉には、草津の人と町への深い愛情がにじんでいました。湯に浸かる時間の背後にある支えを知ること。それが草津をより豊かに味わうきっかけになるのだと思います。