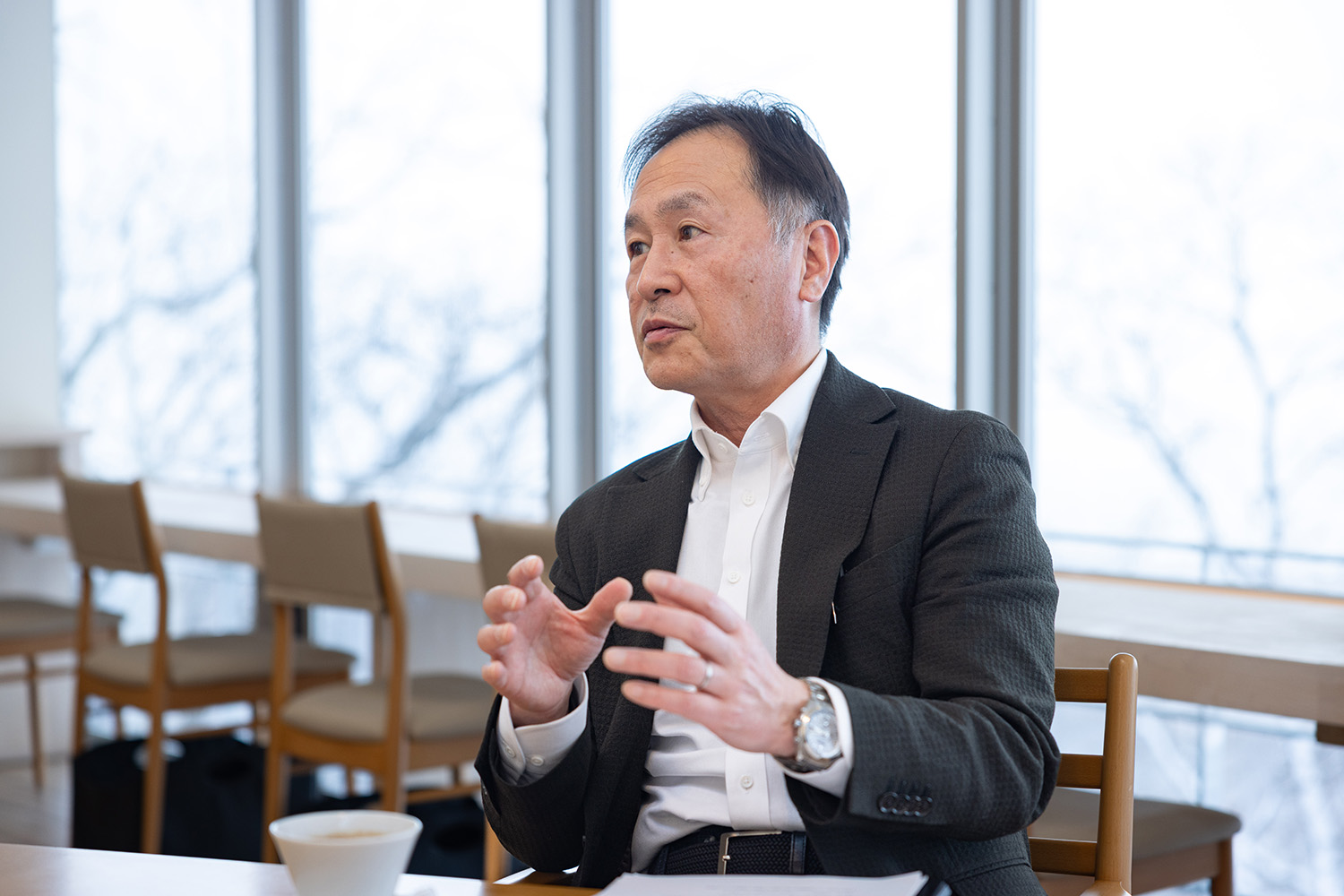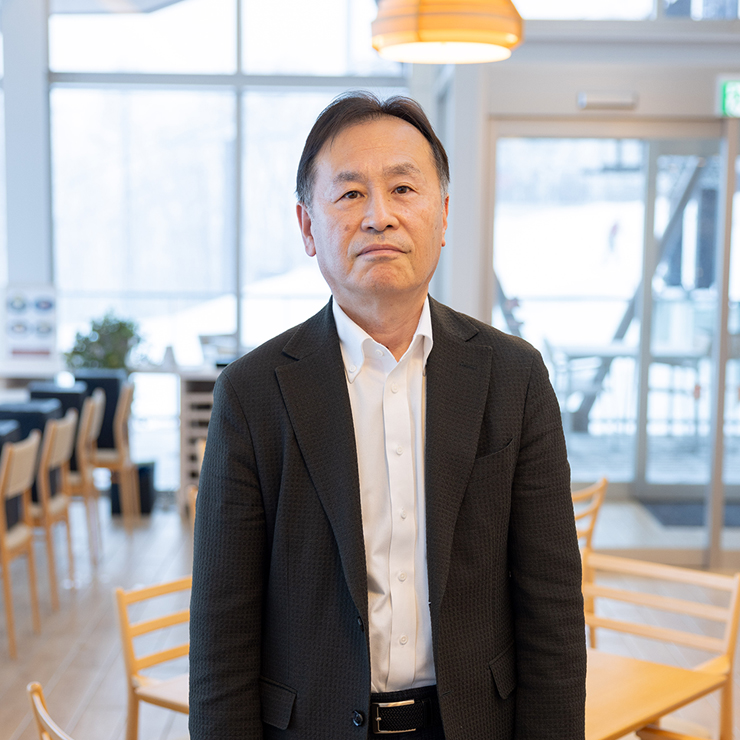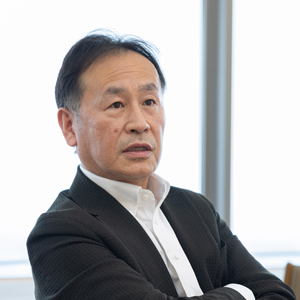
堀田洋一さん
会社を継ぐ選択を迫られUターン。挫折を経てヒット商品が生まれるまで

草津町出身の堀田さんは高校進学を機に町外へ出られたのですね。
堀田: そうですね。中学までは草津で過ごし、高校は前橋市へ進学し卒業後は東京へ出てコーヒーチェーン店に就職しました。実は、父が草津で「草津名産品製造」という土産の卸業を営んでいたのですが、私が30歳手前の頃、父から東京にこのまま残るのか、それとも草津へ帰って会社を継ぐのかの選択を迫られまして。「お前が帰ってこないなら弟に渡す」と言われてしまったんです。
その言葉で草津へ帰る意思が固まったのでしょうか?
堀田: 実はすごく悩みました。当時は2つの店舗を任されていて、さらに地区次長に昇格する話もあったんです。そうなるとエリア全体を見る責任が生まれますよね。その重圧を感じるうちに、「自分にこのまま続けていけるのか?」という不安が大きくなっていきました。それならいっそ草津に帰って会社を継いだほうがいいのではないかと思い、帰ることを決めたんです。
当時はどのような気持ちで草津に戻られたのでしょうか?
堀田:正直なところ、最初は「自分なら何でもできる!」と錯覚していました。東京では店長として営業利益を上げ、表彰されたこともあったので、それなりの実績もありましたし、完全に有頂天になっていましたね。でも、いざ会社を継いでみると、全然思い通りにいかずに叩きのめされました…。
叩きのめされた、というと…?
堀田:当時の草津もバブル真っ只中でしたから、お土産はあればあるだけ売れる状況でした。そんな中、深く考えずに目の前の仕事だけをこなしていたんです。でも、環境が変われば、人の考え方も全く違う。特に、私は社長の息子という立場だったので、周囲の方もいろいろと思うところがあったと思います。父の仕事ぶりを見て、コツコツやることの大切さを学びましたね。

その後、堀田さんがお土産事業で飛躍するきっかけになるものがあったのでしょうか?
堀田:2011年、JRと地方自治体が共同で実施する大型の観光キャンペーン(群馬ディスティネーションキャンペーン)がありまして、それを機に「何か新しいものを作らなければ」と考えたんです。これは千載一遇のチャンスだと。
実は、草津にはこれまで地元の食材を使ったお土産があまりなかったんですよね。でも、以前から「地元産の素材を使って何か作れないか」と個人的にも思っていました。当時、同じ吾妻郡の旧六合村(現在の中之条町)にある「やまぐち農園」さんから花豆を仕入れていたのですが、そこでは出荷できない規格外の花豆を加工して「花豆アイス」として活用していたんです。その話を聞いて、「うちでも花豆を使った加工品を作れないか?」と漠然と考えました。協力していただいていた工場に相談したところ、花豆をペースト状にすることができると分かり、それをどう活かすか考えていたんです。
新しい商品が生まれる予感がします。
堀田:そんな時、北陸のある菓子メーカーの社長さんと話をする機会があり、「バウムクーヘンに練り込んでみたらどうか」という提案をいただきました。こうして生まれたのが「花豆ばあむ」※で、発売当初は年間1万5千~2万個ほど売り上げる人気商品を生み出すことができました。
当時から草津ならではのお土産といえば、やはり温泉まんじゅうや花いんげん甘納豆が定番で、今もこの2つは今も王道です。ただ、当時は「花豆ばあむ」が加わったことで、会社の業績も上向き、各方面で取り上げてもらう機会が増えました。ヒット商品が出ると類似品も登場することが多いのも事実ですが、それは決して悪いことではなく、新しいものが生まれ、さらに良いものが生まれる流れにつながるんです。「花豆ばあむ」の誕生がその潮流を作れたのは良かったなと自負しています。
※現在は販売終了
時代の変遷を遂げ、町全体が新しい景色を目指していく

堀田さんが幼少期の頃、記憶としてある草津はどんな町だったのでしょうか?
堀田:実はあんまり覚えていないんですよ。とにかく野球少年だったから、練習に打ち込んで空いた時間に勉強して……といった生活でしたね。
ただ、幼いながらも、草津町には“二大派閥”が存在していることは認識していました。どちらの派閥につくかで生活がガラッと変わる、そんな時代でした。実際、私の叔父が町長を務めたことがあり、彼の伝記の中にもその経緯が記されています。この派閥争いは1990年代前半くらいまでは続いていたと記憶しています。ただはっきりと断ち切られたのは、現在の黒岩町長になってからだと思いますね。
小さいコミュティならではの苦労があったのですね。当時の観光客の傾向はどのような感じだったのでしょうか?
堀田:当時は社員旅行や団体旅行がとても多かったですね。ひとつのホテルで1,200人以上を受け入れることもあったそうです。一部屋に10人くらい宿泊するのが普通で、ホテルの中にある売店やラウンジはもちろん、歌謡ショーが開催されたりして、いろいろアクティビティが充実しているため、ホテル内ですべてが完結してしまう。だから観光客がホテルから外出する必要がない状況でした。
今とはかなり違う状況ですね。
堀田:そうですね。今は団体で訪れるお客様が減りました。多くても10人くらいでしょうか。そもそも、大人数を受け入れるホテルや旅館がほとんどなくなっている印象です。
今の草津は時期を問わず常に観光客で賑わっていますよね。その要因は何だと思いますか?
堀田:実は、黒岩町長が町議会議員で議長を務めていた頃、「町長になったら新しい景色を作りたい、魅力ある景観を作りたい」とおっしゃっていたんです。そのビジョンのもと、湯畑周辺の整備が進められました。例えば、湯畑に隣接していた駐車場を撤去し、共同浴場「御座之湯」や「湯路広場」を整備するなど、さまざまなインフラ整備に挑戦しました。有言実行したその結果が今の賑わいの要因になっていると感じていますね。

湯畑の整備だけでなく、町全体に目新しさがあるのも草津ならではだと思います。
堀田:2010年度から「街なみ環境整備事業」に取り組み始めたことが大きな転機だったと思います。メイン通りだけでなく、小道や路地裏にも気を配り、観光客が歩きたくなるような政策を進めました。
その結果、町の景観に合ったデザインを考えるようになり、自分たちの地区ごとにルールを作ったんです。例えば、屋根の勾配を決めたり、外壁の素材を統一したりといった取り組みです。町の予算を活用しながら建物を改修していくことで、一カ所が変わっていくと、周りも次々と変化し続ける。この積み重ねが、今の草津を作っているのではないでしょうか。
草津を訪れる観光客の方に「どうして草津に来たんですか?」と聞くことがあるのですが、「町の雰囲気がいい」「景色がいい」、そして「温泉が素晴らしい」という声が多いんです。それに加えて、「草津にいる人がいい」と言ってもらえることも多く耳にすることが増えました。お客様あっての草津ですから、そういう思いが伝わっているなら、とてもうれしいですね。

堀田さんが考える、草津が直面する課題にはどのようなものがあるのでしょうか?
堀田:やはりインフラの問題が最も大きいですね。2023年度には観光客が370万人に達しました。バブル期の300万人と比べても、20%も増えている。今年は400万人に届く勢いです。
そうなった時に、やはりインフラの整備が追いついていないことが問題。例えば、2024年に水不足が発生しました。特に3月は学生旅行のシーズンで観光客が増え、ホテルや共同浴場でのシャワー使用率が圧倒的に上がるんです。それに加えて老朽化による漏水も発生し、町全体の水が足りなくなってしまいました。また、下水道の整備には莫大な費用がかかりますし、駐車場不足の問題もあります。
そして人口減少も深刻な問題です。私が草津に戻ってきた時は人口が1万人弱いましたが、今では6,000人ちょっとになってしまいました。2035年には4,000人を下回り、「消滅可能性自治体」になるおそれも指摘されています。さらに後継者不足も深刻です。観光客が増えても町の基礎人口を増やさなければ、草津の存続は危ぶまれます。そのためには、定住してくれる人へのホスピタリティをしっかりと整備していく必要があるのではないでしょうか。
夢にも思わなかった今の立ち位置。“未完成”な草津の魅力をシンプルに伝えたい

堀田さんが代表を務めている「草津観光公社」について教えてください。
堀田:もともとは「草津開発協会」という名前でしたが、1990年4月に「草津観光公社」として新たに設立されました。現在はバスターミナル、草津体育館、スキー場、ゴルフ場、道の駅、大滝乃湯などの観光施設を運営しています。
最近では、草津の新しい観光スポット「裏草津」にあるカフェ「月の貌(つきのかお)」も弊社が運営しています。全9つの施設を合わせると、従業員は約300人ほどになりますね。
代表取締役社長に就任されたのは2024年1月とのことですが、どのような経緯で代表になられたのでしょうか?
堀田:実は、まさか自分が観光公社の経営に関わることになるとは夢にも思いませんでした。ただ、当時の会社の状況が大変だったことは聞いていたんです。
2022年の秋頃、黒岩町長が観光公社の代表を兼任していたのですが、後任を探さなくてはならないのに、頼んだ方々に断られてしまったと伺っていました。当時、私は「草津名産品製造」の代表をしていましたが、後継者がいないことやコロナ禍の影響もあり、どこか別の会社に事業を引き継いでもらうことを考えていました。でもなかなか引き継ぎ先が決まらなかった。そんな話を町長としていたところ、「適任の後任を見つけた!」と言われて。誰のことかと思ったら、私の名前が挙がったんですよ(笑)。
まさか自分だとは思わず(笑)
堀田:そうなんです。最初は「いやいや、自分の会社もあるし無理ですよ」とお断りしたのですが、「もし草津名産品製造を引き継ぐ会社が見つかったら考えてくれないか」と言われました。そして2023年、引き継ぎ先が見つかったことを機に、改めて「とても名誉なことですし、私で良ければお受けします」と町長に返事しました。もちろんすぐに代表になったわけではなく、引き継ぎ期間などを経て、2024年1月に観光公社の代表に就任しました。
就任してからまず取り組んだことは何だったのでしょうか?
堀田:2023年12月に天狗山山頂にオープンした寿司レストラン「クリスタル天(ソラ)おおぜき」の経営をしっかり軌道に乗せることを町長から直接お願いされました。ここは草津の新しいランドマーク的な店で、標高約1,300mという日本一高い場所で、東京・築地と豊洲から直送した新鮮なネタの江戸前寿司が味わうことができます。ゲレンデ内にあるため、冬以外のシーズンも立ち寄ってもらえる店になるように、予約者にはゴンドラ料金を無料にしたり、町内の無料送迎などのキャンペーンをいろいろ導入。草津に訪れるたくさんのみなさまに、お店の存在を知ってもらえるような新しい取り組みに挑戦しています。

就任から約1年が経ちますが、町長が堀田さんを選ばれた理由は何だとお考えですか?
堀田:これは私の勝手な憶測ですが……、黒岩町長と私は経営に対するスタンスが似ているのかもしれませんね。ある意味、オーソドックスでシンプルな考え方を徹底しています。
町長の場合は、それに加えて情熱や知識も持ち合わせていますよね。町長からは「経営のセンスもあるし、数字も読めるから」と言っていただき、本当に光栄なことです。
経営が大変な中での就任となると、プレッシャーも大きかったのではないでしょうか?
堀田:そうですね。その点は、代表取締役の役職を受ける時から覚悟はしていました。「草津観光公社」は、町が88%の株式を所有する第三セクターです。負債はありますが、民間企業とは違う部分もあるので経営的なプレッシャーはそこまで大きくないのかもしれません。ただ、町の経済を支える施設を多く運営しているため、経営状況によっては町全体に悪い影響も与えてしまう。だからこそ、強い責任感を持って臨まなければならないと思っています。
町長は「草津町に完成はない。常に未完成」とおっしゃっていて。現状に満足してしまったら、それは衰退の一途をたどる。我々も町が投資してくれることに甘んじるのではなく、共にビジョンを共有しながら働いていきたいです。
自らの経験を活かし、草津の新たな名物を続々と生み出す
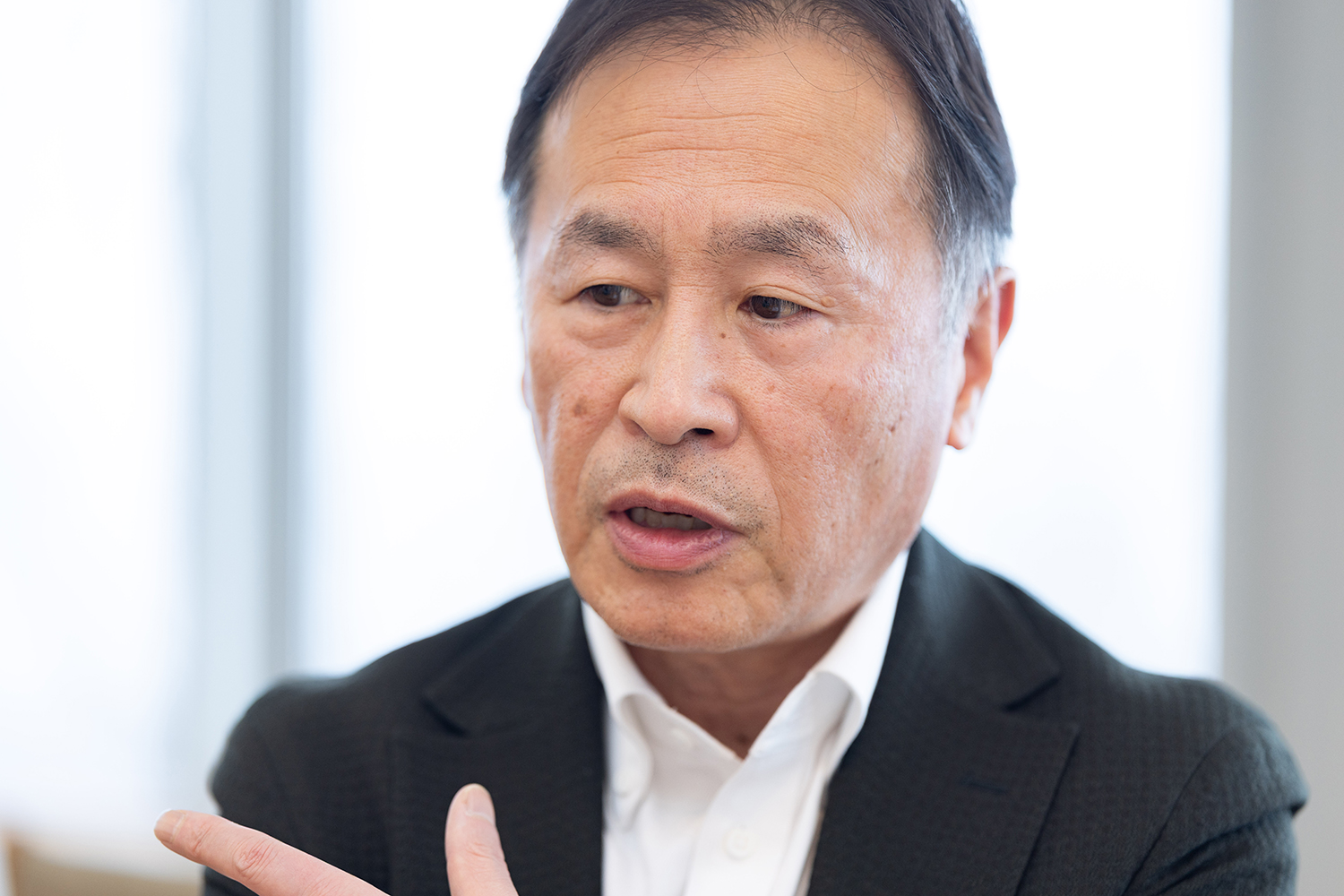
代表に就任されてから、新しいお土産の開発も盛んにされていますよね。
堀田:私の会社を引き継いでくれた会社の代表が、「草津に何か恩返しをしたい」ということをきっかけに、草津温泉を象徴する景色を4つの色をテーマにした「くさついろに染まるプロジェクト」を立ち上げました。そのプロジェクトを具現化するため、高崎市にある「まちのわーくす」という会社と協力し、「草津ならではの商品を作ろう」となったのです。
どのようなコンセプトで商品開発を進めたのでしょうか?
堀田:草津にはさまざまな「色」があることにクローズアップし、その色を身に付けることで記憶に残る、思い出になる旅にしようというのがコンセプトです。例えば、温泉をイメージしたグリーン、裏草津はイエロー、湯畑のライトアップのパープル、シャクナゲのピンクといった具合に、4つの色を軸にした商品を展開しています。そこから手ぬぐい、サコッシュ、コンパクトミラーなどを制作し、弊社が運営する温泉施設や道の駅で販売を始めました。

草津の魅力を色で表現するのは面白いですね。最近では「草津温泉餃子」も発売されたと聞きました。
堀田:そうなんです。もともとお土産としてラーメンはあったのですが、「ラーメンがあるなら、セットで餃子も食べたいよね」と(笑)。でも、一般的な餃子では面白くないので、草津だからできるこだわりを加えて開発しました。
どのような点にこだわりが?
堀田:まず、皮には「浅間酒造」の日本酒仕込み水を使用し、キャベツは嬬恋産、肉は赤城の上州豚で餡を作っています。それに加えて、インパクトを出すために通常の餃子の約2倍、約40gのジャンボサイズにしました。職人の手作りを徹底して、皮のもちもち感、餡のジューシー感にもしっかりこだわっています。
こうした新しい商品を次々と生み出していくのは、やはり堀田さんの得意分野なのでしょうか?
堀田:そうかもしれません。町長が私を観光公社の代表に指名してくれた理由にも繋がると思いますが、食には私自身もともと興味がありますし、こだわりも強いんです。物販に関してはずっと関わってきましたから、今までの経験が活かされていると思いますね。
ドッグツーリズムにも熱視線。先人が守ってきた歴史を守り、これからも進化させていく

今後の商品展開についての展望はありますか?
堀田:化粧品の中でも、特にオールインワンゲルに力を入れています。熊本にある化粧品製造会社と協力して、草津温泉の源泉水を使用して作った「草津温泉オールインワンゲル」を2024年に販売したのですが、これがとても好評でリピーターが増えました。今後も化粧品分野には力を入れていきたいと考えています。
観光としての新たな取り組みにも期待しています。
堀田:実は、今まで草津になかった動物病院がこれから開業することをきっかけに、以前から考えていた飼い主と犬が一緒に旅行を楽しむ「ドッグツーリズム」にも力を入れていく予定です。すでにスキー場の一部にドッグランを設置して、グリーンシーズンに利用できるようにもなっているんですよ。ただ、草津温泉には意外とペットと泊まれる宿泊施設が少ないんです。その代わり、北軽井沢にはペット同伴可能な宿が多くあるので、そうした施設とタイアップした企画も今後考えています。

新しいトピックが次々と生まれていますね。
堀田:そうですね。群馬は温泉大国ですから、草津がこうした取り組みをモデルケースとして成功させれば、「草津ができるなら、うちの温泉地でも」と続く地域が出てくるかもしれません。そういうきっかけになったら、とてもやりがいを感じますね。
最後に、堀田さんが思う「くさつびと」の気質とは?
堀田:商売に関しては少し飽きっぽいところがあるかもしれませんね(笑)。これは草津に限らず、日本人全体に言えることかもしれませんが。
ですが、その一方で草津には気持ちが温かい人が多く集まっています。そして、先代や先人たちの想いを受け継ぎ、温泉という貴重な資源を守り続けてきた。その意思を持って観光客のみなさんに接している人もたくさん町を支えています。その気持ちを少しでも感じてもらえたなら、「くさつびと」のひとりとしてうれしいですね。
草津を代表する施設を数多く運営し、代表という立場ならではの重圧やプレッシャーさえも原動力に変えて、新たなアイデアを生み出し続ける堀田さん。草津の持つ可能性を信じ、その未来に大きな伸びしろがあることを強く感じさせてくれました。