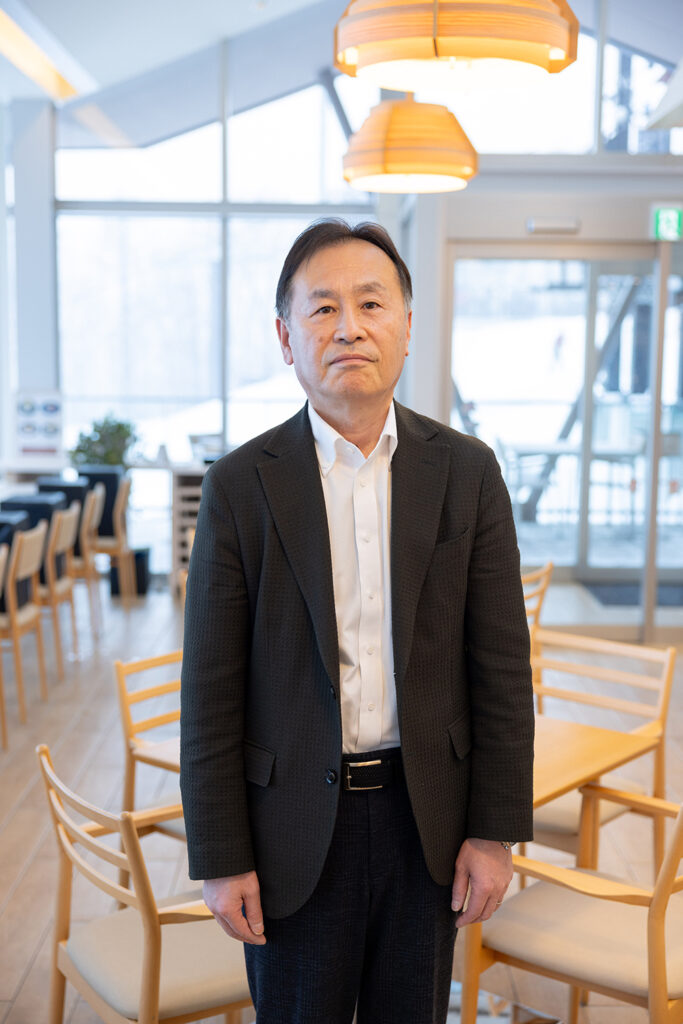安齋 浩さん
進学を機に草津町を出た10代。がむしゃらに駆け回った会社員経験が大きな糧に

代々続く酒店の息子として幼少期を草津で過ごした安齋さんが、進学を機にこの場所を離れた時のことを教えてください。
安齋:草津町には中学校までしかないので、高校進学からは町外に出るしかないんです。今は距離が遠くても自宅から通っている子も多いようですが、僕の時代はある程度の距離を超えると下宿が当たり前。僕は県立渋川高校へ行き、その後も草津へは戻らず東京の大学に進学し、そのまま都内で就職しました。それがたまたま業務用の酒販店だったんです。
それは家業を継ぐためにあえて?
安齋:実はその考えはあんまりなかったんですよ(笑)。今思えば高校生の時まではそういう気持ちもありましたけどね。でも、酒販店で働く中で徐々に継ぐのかな、っていう思いが芽生えたのかもしれません。
酒販店ではどんな業務を?
安齋:東京のとある業務用酒販店に勤務し、営業を担当しました。業務用ですから飲食店さん(居酒屋、スナック、レストラン、カラオケなどがお客様)ですが、商談するにもお店のオープン前とかクローズ後でないと対応してもらえないので、拘束時間が大変なことになっていました。それに、当時は集金作業も自分たちで行っていたのですが、これが営業業務を煩雑にしていたように思います。あと営業が商品を営業車に積んで納品する事もわりとあったんですよ。僕も1年、2年、3年と年を追うごとに、「この仕事は若くないとできないな……」と実感せざるを得なかったですね。
なかなかのハードワークだったのですね。そんな大変な業務の中でも得たものがあったのでしょうか。
安齋:それはもう得たものだらけでした。特に当時の先輩には感謝してもしきれないほどです。私は営業の中でも商品知識が一番ある人の近くにいたので、お酒に関するいろいろな情報を教えていただきました。その先輩の影響で、世界の洋酒が膨大に載っている『世界の名酒事典』を暇な時にパラパラ読んでいたら、自然と知識がつくようになって。別にお酒の種類を覚えるのが必須ではないんです。ただ、やっぱりお客様からこれってどんなお酒なの?って聞かれた時にパッと答えられる。そういう意味でも無駄じゃなかったし、今に活きていると思います。
今のようにネットが普及していない時代だったので、紙ベースで得た知識を実際にお得意先の飲食店で呑んで確かめていくというような感じでした。

営業以外の業務も経験されたのですか?
安齋:配送業務も経験しました。4トントラックに満載とか、とんでもない量のお酒を運んでいましたね。あとは倉庫で商品の品出しとかピッキングの手伝いもしましたよ。ピッキングも、今みたいにバーコードで管理されていなかった時代なので、商品名から探して当てないといけなかったから、今振り返れば人海戦術で取り組んでいたのはよき思い出です。まだ和酒であれば日本語なので分かるのですが、洋酒はフランス語とかドイツ語じゃないですか。ただ、僕は『世界の名酒事典』を見ていたこともあって、だんだんと「あの時見てたやつはこれか!」と今まで溜め込んでいた知識が一致しはじめ、点と点が繋がった瞬間をいくつも経験しました。
「“草津出身”を誇りに」Uターンを決意した30歳

東京で暮らす中で、草津への思いに変化はあったのでしょうか。
安齋:実は、高校に行っていた時に草津温泉出身だと言うと、「あんな山の中から来たんだ」と結構言われていたんですよ。「あぁ、やっぱり草津ってメジャーじゃないんだな」って思っていたのですが、東京だと反応が全然違ったんです。「知らないと思いますけど、草津温泉出身で…」と言うと「いやいや、めちゃくちゃ有名じゃん」と。まさか東京という大都市でそんなに認識されていることに驚きました。
草津は観光地として昔から一流だったと。
安齋:そうなんです。思えば僕が子供の頃、どこの温泉地もバブル経済の影響で設備投資をガンガンして、それに比例してお客さんもガンガンきていた時代があって、それが今となっては負の遺産になっている場所もあったりして・・・。そう考えると、草津の今があるのは、そんな時代も耐え続けて踏ん張ってきた諸先輩方のおかげだなと感じていますね。
そして30歳の時に退職し、草津へのUターンを決意したのですね。
安齋:戻った当初のテンションは結構低めでしたね。町に戻ったはよいが、そもそも店をどうしたらよいのかも漠然としかなかったんです。でも、純粋に長年続く「安齋商店」の歴史をこのまま終わらせてしまうのはもったいないと思いました。
家業を継ぐことになり、まず取り組んだことは何だったのでしょうか?
安齋:当時から業務用卸販売がメインではあるものの、店舗での売上もそこそこキープできていました。朝から夜の9時くらいまでオープンしていて、その時間はほぼ一人でやっているような状態だったので、その中で自分はここの場所で何ができるだろう?と考えた時、商品のラインナップを積極的に変えていこうと決めました。

どのように変えていったのでしょうか?
安齋:店を訪れた人の気持ちを考えて、日本酒は群馬産のものを積極的に取り入れていました。ただ、当時群馬産の地酒はあまりメジャーではなかったんです。もちろん有名な蔵元はいくつかありましたが、全国的な知名度はまだまだ低くて。そんな中で、吾妻郡にある3軒の蔵元のお酒を仕入れて販売していました。それに加えて僕が洋酒好きだったので、今まで少なかったワインの種類も充実させたり。その一方で近隣のホテルや料理店さんなど、卸先のお客様をどれだけ増やせるかという点にも力を入れました。今思えば、戦略とか戦術とかはあまり細かく考えず、お客様がどうしたら喜んでもらえるかを最優先してましたね。
コロナ禍のリニューアルオープンが大きな転機に。常に観光客で賑わう理由は“遊び心”にあり

そして、2021年のリニューアルオープンは大きな転換期になったように思います。
安齋:そうですね。リニューアルの話を進める段階から、「20代、30代の若い世代の方が入りやすい店舗にしたい」という思いはありました。妻や設計士さんと相談しながらこんな雰囲気にしたいと決めていったのですが、建物が完成するまでの道のりが長かったですね。
何かトラブルに見舞われたり?
安齋:元々ここは草津町初の鉄筋コンクリート造りのビルとして祖父が建てたんですよ。そういう意味でも貴重な建物ということで、当初は建て替えではなく骨格を残してリフォームにしようという計画でした。ただ、1カ月ほど解体作業が進んだある日、業者さんから連絡がきて現場に行ってみたら、「これ以上進めると建物が崩壊する可能性があります」と言われてしまいまして……。
そこで決断を迫られたわけですね。
安齋さん:はい、そこに居合わせた人たちが全員黙っちゃって。仕方がないので、僕が「取り壊すしかないですよね」と言うしかなかった。あの時の空気の重さはいまだに忘れられないです(笑)。結果的に設計もゼロからやり直しになってしまい、当初の予算よりもかなりオーバーしてしまいました。ただその結果、設計に制約なく建て直すことができたので、今振り返ればとても良かったと感じています。

制約なく建て直すことが功を奏したと。建物のデザインは最初からイメージしていたのですか?
安齋:そうですね、最初からこの建物の形はイメージとしてありましたし、元々コンクリート造りだったから、新しく建てるなら木造を希望していました。木の温もりを感じる外観や、天井が高くて開放感がある内装もとても気に入っています。実はここの立地は西日が強く当たるので、商品が傷まないよう建物自体を斜めに角度を付けて西日の影響を直接受けないように設計してもらいました。
コロナ禍でのオープンに不安な部分もあったのではないでしょうか。
安齋:そりゃもう妻からは「ホントに建てるの?」って何度も言われましたよ。どこもかしこもお店が閉まって閑散としている状況ですから。これからどうなるか誰にも分からないなか、妻の心にも波風を立たせてしまいました。さらに当初のオープン予定より3年近く伸びてしまって、本当に生きた心地がしなかった日々だったけれど、なぜか自分の中では「大丈夫」っていう自信があったんですよね。
そこには成功するという根拠が……?
安齋:周囲からは「コロナ危機で店舗経営がダメになっても“業務用酒販業”は残せるはずだから、店舗にそこまで予算をかけなくても……」と言われましたが、この場所は湯畑に近いのがメリットだし、そんな好立地で“対お客様”の部分がごっそり抜けてしまうのは、あまりにももったいないと思ったんです。
一方で、業務用のお客様に対して「こんなお酒があって、テイスティングもできますよ」という情報発信の基地になればいいなと伏線も考えていました。ありがたいことにリニューアルオープン後は、多くの観光客の方たちに立ち寄っていただけるようになりました。ただ残念なのは、まだ業務用のお客様に対しての試飲会や勉強会を行えていない事で、これは今後の課題ですね。
結果的に多方面から支持されるお店になりつつあるんですね。
安齋:そうですね。この店で日本酒を初体験してもらったり、自分好みの味を探したりと、お酒との新たな出会いの場を生み出したいと考えています。また、群馬や近隣エリアを中心に「これ面白いぞ」というお酒の関連アイテムを店頭に並べているので、多角的な面でお酒に触れ合ってほしいですね。

そういったものの情報収集はどこから?
安齋:それこそSNSから知ることも多いですよ。それと、家族旅行の途中で寄ったサービスエリアでやたら売れてるお菓子があって、買って食べてみたらめちゃくちゃうまかったから、店に置くために会社に直接連絡して仕入れさせてもらいました。これに関しては宮城県のものだから群馬とは全然関係ないんですけどね(笑)。
でも、常に何かおもしろいことを探す意識が大切だったりしますよね。
安齋:そうなんです。無意識に過ごしていたらそのまま流れてしまうことも多いから。洋酒に関しても「こんな山奥の温泉街に置いてあって誰が買うの?」っていうウイスキーとかも結構あるんです。日本に100本しか入ってきてないものとか。仕入れたはいいけど管理に手間はかかるし、果たして売れるのか?というアイテムもあるけれど、お客様にとって店側の“遊び心”がないとつまらないなと思うんですよ。
お客様に楽しんでもらえることが第一だと。
安齋:ネットでしか見たことないお酒が店頭に並んでるのを初めて見た、というお酒好きの方がリピーターになって足を運んくださったりもして。高く仕入れたお酒が売れないと経営的にはマズいですけど……でも、うちは業務用販売が主体となっているので、そこが元気であれば店舗でもそういう遊びができる。だから、ハードルが高いと思われがちな酒店への入店を、実は気軽に入っていいし、実は面白い所なんだよ、っていうのが伝わればいいなと思っています。
店内には試飲スペースやカフェコーナーがありますよね。草津を訪れる方を繋ぐ場所になっている気がします。
安齋さん:試飲スペースに関しては、一杯飲めるバーカウンターを兼ねたものにしたいとオープン当初は想定していたんです。試飲といってもそんなにたくさん訪れないだろう、と思っていたんですが、ありがたいことに予想以上にたくさんのお客様にご利用いただいて、バーとして利用するのは人員的にもちょっと難しくなってしまいました。

予想外ではあったけれど、それだけ反響が大きかったという証拠ですよね。
安齋:そうですね。実は店の裏手に古い蔵があるのですが、そこをリフォームしてバーをやる計画があるんです。まだ本格的に稼働ができていないのですが、2階にサーバーを置いて、コインを入れるとワインが出てくる、いわばセルフバーのようなもの。その蔵とは別に店舗を増築しまして、そこでは赤ちゃんや小さなお子さんがいるお母さんが使えるトイレや授乳スペースも併設して、若い家族連れにも利用してもらえたらなと考えています。コンセプトとしては、なるべく人の手を介さないように、スタッフも常駐せずキャッシュレス対応ができたらと思うけれど、それがどこまで通用するかがこれからの課題でしょうか。
これからも“お酒”を通して、お客様を喜ばせ続けたい

安齋さんは、草津の観光客が増え続けている要因はどんなところにあると思いますか?
安齋:何でしょうね……。今なお変化し続けているところかな。ハード面に関しては、過去に失敗もたくさんあったとは思いますが、新名所といわれる場所ができたりして、観光客を楽しませる要素がたくさんある。安齋商店もそんな場所になりたいです。
時間をかけてわざわざ草津に来たいと思わせる理由は、草津にいる“人”にもあるような気がします。
安齋:そうですね、もてなしたいという気持ちはみなさん強いと思います。それと、前に町のアンケートでも見たのですが、草津を訪れる方の大半は、東京、神奈川、千葉、埼玉といった、いわゆる首都圏からなんですよ。そういった方たちを迎え入れているから、流行に敏感な人が多いのかもしれませんね。
なるほど。そして草津の人々は「働き者で根性がある」ように感じます!
安齋:働かざるを得ない状況というのはあるかもしれないですけどね。でも、高校から町外に進学なり就職で出て、外の世界を見てからUターンして来る人も多いから、根性が座ってる部分はあるかもしれない。もしくはそういう気質が草津町民のDNAに組み込まれているのかもしれませんね。

5年後、10年後の草津について、安齋さんの中で「こうなっていたらいいな」という展望はありますか?
安齋:やっぱり草津で働きたい人や移住者が増えてくれたらうれしいです。草津の人口は約6,000人と少なく、その中で働ける人の数は限られている。そして草津には年間370万人以上の観光客の方に来ていただいているという現状があります。この先も観光地として支持される場所であり続けるためには、ソフト面が充実してないと十分なおもてなしはできない。そのためにも整えなくてはいけない部分がたくさんあるんです。
未来の“くさつびと”への支援が必要なのかもしれません。
安齋:そうですね。現在は医療施設が不足しているのが現状で、特に産婦人科は車で1時間かかる場所にしかなく、かなり切実な問題。そして、若い人たちが遊べるような場所が近くにないですし。そのあたりも含め、定住したいと思ってもらえるような町づくりを進めていく必要があるんじゃないかな。子育て環境も自然もあるし、満員電車もなく意外と良いと思います。まだまだ改善できる余地はありますが。
お店のことや町のこと、安齋さんのやるべきことはまだまだ尽きないですね。
安齋:そうなんです。こういうことに終わりはないですから。でもやっぱり、お店に足を運んでくれる方はもちろんですけど、草津で泊まったホテル旅館や食べに行った飲食店さんを通してうちのお酒を飲んでくれた、ということも含め、いろんなツールを通してお客様によろこんでもらえる酒販店であり続けることが、永遠の目標です。
今ある現状に決して満足することなく、新しいこと・面白いことを探し続けている安齋さん。その姿勢と人柄が反映されたお店にたくさんの人たちが集まり、楽しそうにお酒を選ぶ姿が印象的でした。

アクセス:草津温泉バスターミナルから徒歩3分
住所:群馬県吾妻郡草津町草津67
営業時間:10:00-18:00
定休日:火、水、木曜日